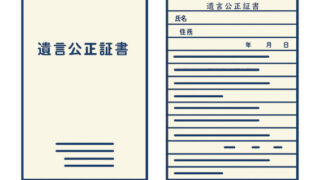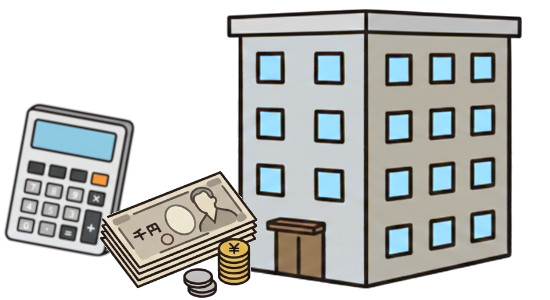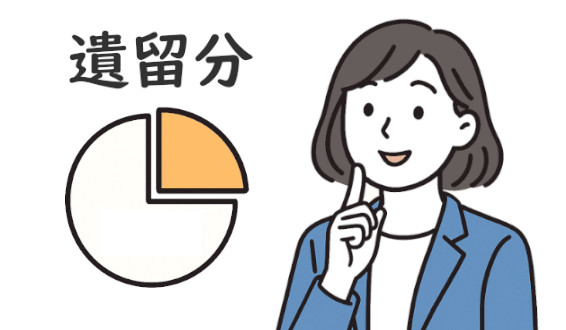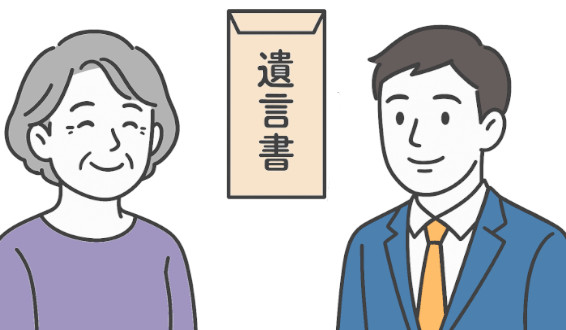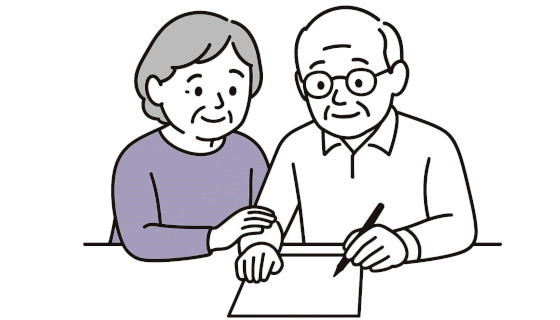「遺言書を作りたいけれど、どの方式を選べばいいの?」
遺言には3つの方式があり、それぞれ特徴やメリット・デメリットが異なるため、目的に合わせて選択することが大切です。この記事では、自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言の違いを比較し、「どの方式を選べばよいのか」を司法書士が分かりやすく解説します。
1.遺言は、主に3種類ある!
遺言とは、あなたの財産を誰にどれだけ渡すのかを、書面で示すものです。あらかじめ口頭で家族へ希望を伝えていたとしても、形式を満たした遺言を書かなければ、法的な効力は生まれません。
そして、よく利用されるのは次の3つの形式です。次章で詳しく解説していきます。
➀自筆証書遺言 ②公正証書遺言 ③秘密証書遺言
| 自筆証書遺言 | 公正証書遺言 | 秘密証書遺言 | |
|---|---|---|---|
| 作成 | 全文を自筆で書き、署名・押印する | 証人立ち合いのもと、公証人が作成する | 自分で書く。証人が立ち合い公証人が証明 |
| 証人 | ― | 2人 | 2人 |
| 費用 | 0円※1 | 1万6千円~ | 1万1千円 |
| ◎ | 手軽で、費用がかからない | 無効・紛失のリスクがかなり低い | 内容を秘密にできる |
| × | 無効・紛失のリスク | 費用と手間がかかる | 無効リスク・費用がかかる |
| 保管 | 本人 ※1 | 公証役場 | 本人 |
| 検認 | 必要 ※2 | 不要 | 必要 |
| 〇 | ◎ | ✕ |
※2 法務局で保管する場合は家庭裁判所の検認は不要
2.自筆証書遺言とは?
本文を自筆で作成する遺言書のことで、もっとも身近で作りやすいため、世の中の大半の遺言書はこの形式です。手軽に作れますが、無効となるリスクも高いです。
2-1.自筆証書遺言のメリット◎
➀思い立ったらすぐ作れる手軽さ
「気持ちをゆっくりと整理したい」「内容を誰にも知られたくない」という方に適しています。財産の種類が少ない・相続人が少人数など、内容がシンプルなケースで利用しやすいです。
➁費用がかからない
紙とペンさえあれば自宅で手軽に作成でき、
③法務局に預けられる( 自筆証書遺言保管制度 )
1通につき3,900円で保管してもらうことができ、紛失・改ざんのリスクを大幅に減らせます。
2-2.自筆証書遺言のデメリット✔
➀形式不備で無効になりやすい
全文を自筆で書くこと、日付を書くこと、署名押印をすることなど、形式が厳格に決められています。「日付があいまい」「押印を忘れた」などにより、無効になるケースが多く見られます。
➁紛失・改ざん・発見されない
自宅保管の場合、このようなリスクがあります。 内容を知られたくないため誰にも保管場所を伝えず、遺言が発見できなかったという事例もあります。
③家庭裁判所の「検認」 が必要
相続開始後に、相続人が裁判所へ出向く必要があり、時間と手間がかかります。
もっとも、②と③の問題は、法務局の「自筆証書遺言保管制度」を利用すれば解消できます。
3.公正証書遺言とは?
公証役場で、公証人が作成する遺言書のことです。公証人が関与して作成するので、形式不備による無効のリスクがほとんどありません。もっとも確実性が高く、信頼できます。
3-1.公正証書遺言のメリット◎
➀無効になりにくい
公証人という法律の専門家が内容を確認しながら作成するため、書き方の不備によって無効になる心配がほとんどありません。
➁紛失・盗難・改ざんのリスクがない
原本(データ)が公証役場で厳重に保管されるため、安心できます。遺言検索サービスにより、相続人が簡単に探すことができます。
③相続の争いを防ぐ
証人2名の立会い、公証人が意思を確認するため、遺言の真偽や作成過程をめぐる争いが起きづらいです。特に、相続人同士が揉めそうな場合・財産が多い場合・相続人以外に財産を渡したい場合に適しています。
④家庭裁判所の「検認」 がいらない
相続手続きが非常にスムーズに進むのも大きな利点です。
④文字を書けなくてもok
公証人に口頭で内容を伝えて作成することができるので、文字を書けなくても作れます。また、耳が聞こえない、話せない場合でも作成することができます。
3-2.公正証書遺言のデメリット✔
➀費用がかかる
公証役場で手続きを行うため、公証人手数料が必要となり、財産額が大きいほど手数料も高くなります。
➁証人が2名必要
相続人などは証人になれないので、それ以外で信頼できる方を探す必要があります。司法書士や行政書士へ依頼することもできます。
③手間がかかる
事前の打ち合わせや書類収集、証人との調整が必要なため、自筆証書遺言に比べて手間がかかります。
4.秘密証書遺言とは?
秘密証書遺言とは、内容を秘密にしたまま、存在だけを公証役場で認証してもらえる遺言書のことです。内容を誰にも知られずに作成できるメリットはありますが、実務上ほとんど利用されていません。
4-1.秘密証書遺言のメリット◎
➀遺言の内容を秘密にできる
公証人にも中身を見られないため、プライバシーを保ちながら遺言を残せます。
➁文字を書けなくてもok
ワープロやパソコンで作成した文書を使用できます。
4-2.秘密証書遺言のデメリット✔
➀無効になるリスクが高い
内容の不備を誰もチェックしてくれないため、遺言に必要な記載が不足していても、
たとえば、日付の欠落、財産の特定不足、署名の誤りなどの形式ミス
➁家庭裁判所の「検認」 が必要
手間がかかります。
③紛失・改ざん・発見されない
保管は自宅になるため、紛失や発見されないリスクは自筆証書遺言と同様に残ります。
こうした理由から、秘密証書遺言は、特別な事情がない限りあまり推奨されない方式です。
5.遺言の特徴を比較、その選び方
結論から言えば、もっとも確実で安全なのは 公正証書遺言であり、迷った場合はこの方式を選ぶのがおすすめです。
自筆証書遺言は手軽に作れますが、形式の不備で無効になるリスクが高く、自宅保管の場合は紛失・改ざんの心配もあります。財産が少なく、内容がシンプルな人には向いていますが、複雑な相続には不向きです。
秘密証書遺言は、内容を秘密にできるという特徴がありますが、形式の不備で無効になるリスクが高く、費用もかかるためメリットがあまりありません。
一方、公正証書遺言は公証人が関与するため、形式の不備で無効になる心配がほぼゼロ。原本が公証役場で保管されるため、紛失・改ざんのリスクがなく、相続開始後の「検認」も不要で、相続人の負担が大幅に軽減されます。
費用や手間はかかるものの、「遺言の内容を確実に実現したい」「家族に迷惑をかけたくない」という方に最も適しています。
遺言・相続はゆかり法務事務所へ
LINE・メール・微信・電話で
\ 無料相談を受付中 /
東京都足立区千住中居町17-20 マルアイビル 6階 北千住駅から徒歩8分

行政書士
岡野 由佳梨

行政書士 岡野 由佳梨
専門家としての知識だけでなく、人として寄り添う姿勢を大切にし、ご本人にとって最善となるご提案を心がけています。どんな小さなことでも、お気軽にご相談ください。