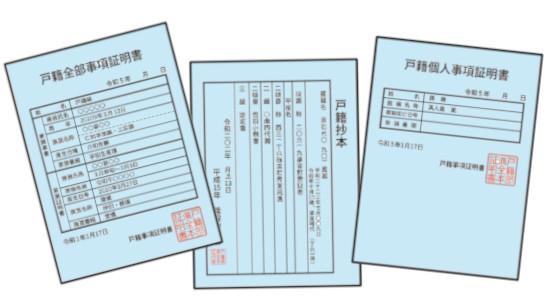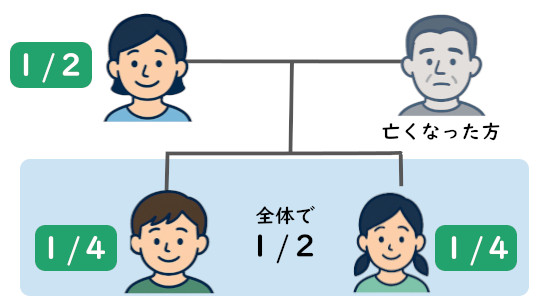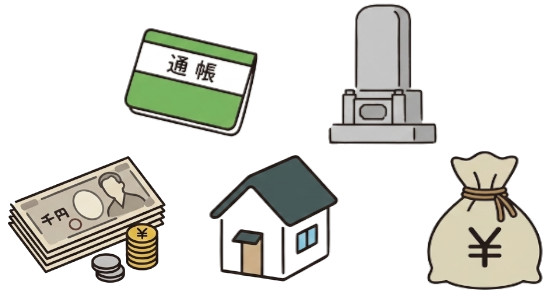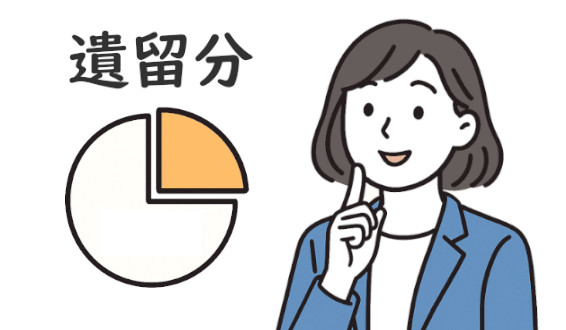相続手続きでは、まず最初に財産調査を行います。財産を正しく把握しないまま相続を進めてしまうと、本来受け取れるはずの保険金を失ったり、思わぬ借金を引き継いでしまうリスクもあります。
相続手続きに精通した司法書士が、行うべき財産調査の方法や必要書類、注意点をわかりやすく解説しますので、ぜひご活用ください。
1.財産調査を怠ると損することも!
保険金の請求漏れや、銀行口座を知らずに放置してしまうと、数百~数千万円もの損失につながる可能性があります。損をしないためには、財産の全体像を正確に把握することが重要です。また、借金も相続の対象となるため、知らずに借金を背負ってしまうリスクを防ぐこともできます。
亡くなった方の家や土地、預貯金、株式、さらには借金など、マイナスの財産も含め全て調べあげます。特に、ネット銀行の口座や遠方の不動産、保険などは見落とされがちなので丁寧に調査しましょう。
2.不動産はどうやって調べる?
2-1.固定資産税納税通知書の確認
不動産調査で、最も手軽な手がかりとなるのが「固定資産税納税通知書」です。毎年6月ごろに、土地や建物を所有している人のもとへ郵送されます。通知書には、その人が税金を支払っている家・土地が全て記載されており、不動産を把握するうえでとても役立ちます。ただし、評価額が低く固定資産税の課税対象外となっている不動産は、載っていない場合があるので注意が必要です。
また、通知書が見つからない場合でも、市役所や都税事務所で「名寄帳(なよせちょう)」という書類を取得すれば、その市区町村にあるすべての不動産が一覧で確認できます。足立区の場合、足立都税事務所で取得することができます。
2-2.登記事項証明書を取得して、名義を確認する
1で紹介した情報だけでは、不動産の権利関係がどのようになっているか分かりません。
そこで必要となるのが「登記事項証明書(登記簿謄本)」です。これを見れば、不動産の所有者や持分、権利関係の詳細まで確認できます。登記事項証明書は、不動産の所在地を管轄する法務局で取得します。足立区の不動産であれば、東京法務局 城北出張所」が担当窓口です。申請は、窓口のほか郵送やオンライン(登記情報提供サービス)でするこができます。
3.預貯金はどうやって調べる?
まずは、遺品や書類の中から通帳やキャッシュカードを探しましょう。足立区にお住まいの場合には、足立成和信用金庫に口座を持っているケースが多いです。
金融機関から届いた郵便物や通知書も手がかりになります。取引明細や口座残高のお知らせなどが届いていないか、丁寧に確認してみましょう。
最近では、ネットバンキングや家計簿アプリを使って、複数の口座をまとめて管理している方も増えています。可能であれば、スマートフォンやパソコンの中も確認し、資産に関する情報がないか探してみてください。
また、各金融機関に直接照会をすることで口座の有無を調べることもできます。取引していた可能性のある銀行に問い合わせ、口座があった場合、残高証明書の発行を依頼します。足立区内に支店がある銀行であれば、最寄りの窓口で対応してもらえることが多いです。
4.借金やローンはどうやって調べる?
プラスの財産だけでなく、借金やローンなどの「マイナスの財産」も相続の対象となるため、確認が必要です。まずは、自宅に借用書や返済予定表、消費者金融からの通知などがないかを探してみましょう。
また、未納の税金や健康保険料がある場合もありますので、地方公共団体などから請求書や支払い通知が届いていないかをチェックし、管轄の役所に問い合わせましょう。
通帳の履歴に「借入」や「返済」の記録がある場合、それが手がかりになることもあります。奨学金や教育ローンなども相続の対象になるため、残高の確認が必要です。
借金はありそうだが、借入先が分からない場合は、信用情報機関に対して情報開示の請求をする方法もあります。具体的には、以下の3機関に対し、所定の申請書・本人確認資料・手数料を提出して照会します。
全国銀行個人信用情報センター(KSC)
株式会社日本信用情報機構(JICC)
株式会社シー・アイ・シー(CIC)
5.その他の財産(株式・保険)の調べ方
株式や投資信託などの金融商品は、証券会社を調査します。まずは、自宅にある取引報告書や郵送物、パソコンやスマホの取引履歴を確認し、取引していた証券会社を特定しましょう。会社が分かったら、各社の相続専用窓口に問い合わせてください。
生命保険についても同様に、保険証券や通帳の引き落とし履歴などを確認して、加入していた保険会社を特定します。契約内容によっては死亡保険金が支払われることがあり、これは原則として相続財産には含まれませんが、相続税が課される場合もあります。
6.調査が終わったら「財産目録」を作成しよう
財産の全体像が明らかになったら、次は財産目録を作りましょう。
財産目録とは、遺産を一覧表のように整理したもので、相続税の申告の際に必要になるほか、遺産分割協議を円滑に進めるためにも役立ちます。決まった書式はありませんが、次の2つのポイントを押さえておくと安心です。
・財産を正確に特定できるように記載する
(例:不動産なら所在地・地番、預金なら金融機関名・支店名・口座番号)
・金額の根拠となる資料を添付する
(例:不動産は固定資産評価証明書、預金は残高証明書など)
裁判所のホームページで、財産目録のテンプレート(エクセルファイル)がダウンロードできますので、活用してみてください。
7.財産調査を依頼した方が良いケース
本記事を読んでいただいて分かる通り、相続財産の調査は意外に労力のかかる作業です。また、専門的な知識がないと漏れや誤りが発生するリスクもあります。特に次のケースでは専門家に頼ることをおすすめします。
・正確に調査できる自信がない
・遠方に不動産がある
・相続人の関係が複雑で協議が進まない
・相続放棄(3ヶ月以内)まで時間的に余裕がない
不安がある方、何から始めれば良いか分からない方は、北千住のゆかり法務事務所の無料相談をご利用ください。足立区・葛飾区の相続に強い司法書士が丁寧に対応いたします。
相続・遺言はゆかり法務事務所へ
LINE・メール・微信・電話で
\ 無料相談を受付中 /
東京都足立区千住中居町17-20 マルアイビル 6階 北千住駅から徒歩8分

司法書士
劉 洋

司法書士 劉 洋
相続、遺言、生前対策など、当事務所にはさまざまなお悩みを抱えた方がいらっしゃいます。法律の話をできるだけ分かりやすくお伝えし、不安が安心に変わるよう丁寧に対応いたします。