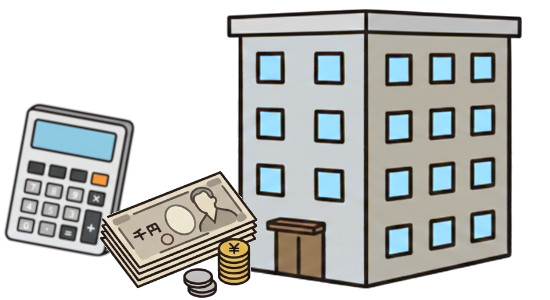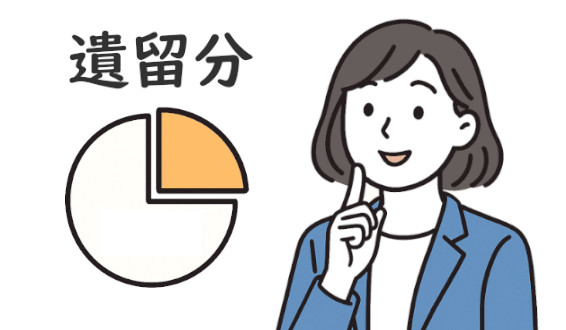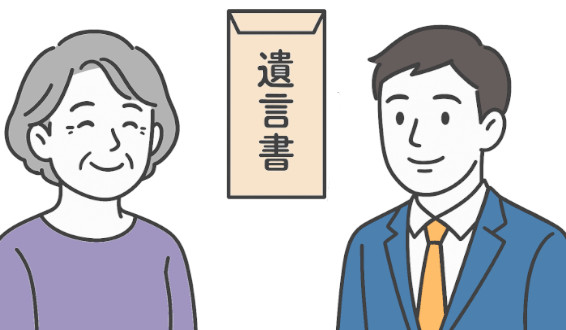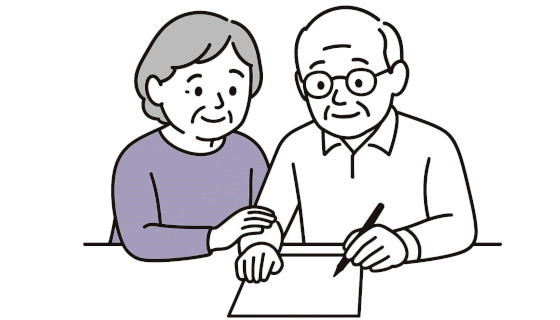遺言書を残しても、それにより「家族に苦労させないか」、「親族間でトラブルになってしまわないか」などのご不安はありませんか?
こうしたトラブルを防ぐ重要な役割を果たすのが「遺言執行者(いごんしっこうしゃ)」です。本記事では、遺言執行者が必要となるケースやその役割などを司法書士がわかりやすく解説します。
1.遺言執行者を指定すれば、遺言を確実に実現できる
遺言執行者とは、遺言に書かれた内容を実現するための手続を行う人のことです。たとえば、不動産の名義変更、預貯金の解約・分配、遺贈の手続きなどを、遺言書の内容に従って進めます。
遺言書を作成しただけでは、相続は自動的に進まず、相続人全員で協力して手続きを行う必要がありますが、その負担は大きいです。そこで、あらかじめ遺言書の中で「遺言執行者を○○と指定する」と明記しておけば、その人に一任することができ、スムーズに手続きが進みます。
2.遺言執行者を選ぶべきケースとは?
遺言執行者は、必ず選任しないといけないわけではありません。しかし、次に挙げるようなケースでは、遺言執行者を選任しておけば、手続きが格段にスムーズに進みます。
2-1.遺された家族に負担をかけたくない場合
遺言執行者が選任される多くの理由は「家族の負担を減らしたい」という思いからです。たとえば、配偶者が高齢であったり、子どもたちが仕事で忙しく、相続手続きに十分な時間を割けない場合などが挙げられます。また、手続きには幅広い知識が必要で、家族にとって大きな負担になります。特に不動産が複数ある場合などは、専門家の助けが欠かせません。遺言書で司法書士などの専門家を遺言執行者に指定しておけば、安心して手続きを任せることができます。
2-2.遺産分割の方法を指定している場合
「自宅を売却して得たお金を子どもたちで分ける」など、財産の分け方に複雑な手順を定める場合です。このような場合、誰か一人が主導して進めようとしても、「勝手に処分した」「不公平だ」といった不信感を招くこともあり、トラブルにつながりやすいです。
2-3.相続人が多い場合
相続人が多いと、手続きを進めるうえで意見の食い違いや誤解が生じやすくなります。例えば、兄弟姉妹が多い場合や、再婚によって相続人が複数の家系にまたがる場合などは、誰が代表して手続きを進めるかをめぐって揉めることも少なくありません。
このような状況で、相続人の一人が代表して手続きを行うと、「財産を独占しているのでは」と疑いをかけられるおそれがあります。その場合、中立的な立場の第三者を遺言執行者に指定しておけば安心です。
2-4.第三者に遺贈する場合
相続人以外の第三者に財産を遺贈する場合も、遺言執行者を指定しておくことをおすすめします。
たとえば、友人や慈善団体などに財産を渡したいとき、相続人がその相手とやり取りをするのは心理的にも負担が大きいものです。場合によっては、「なぜ他人に財産を渡すのか」といった感情的な対立が起こることもあります。遺言執行者がいれば、相続人は第三者と直接連絡を取る必要がなくなり、家族の負担を減らすことができます。
3.このような場合は遺言執行者が必須です!
法律上、必ず遺言執行者を選任しなければならない、とされるケースもあります。これらの手続きには専門的な法律知識が必要なため、司法書士や行政書士などの専門家を執行者として指定しておくことが推奨されます。
3-1.遺言によって認知する場合
子どもの認知は、遺言によって行うことができます。その場合は必ず遺言執行者を選任し、認知の届出を行うなどの手続きを行わせる必要があります。(民法第781条第2項・戸籍法第64条)
3-2.遺言によって相続人を廃除する場合
相続人の中に、遺言者に対して虐待や重大な侮辱をした、また著しい非行を行った者がいる場合、遺言によってその人を相続から外すこと(廃除)ができます。この場合も、遺言執行者を選任し、その人が家庭裁判所に廃除の申立てを行う必要があります。(民法第893条)
3-3.遺言によって一般財団法人を設立する場合
遺言により「一般財団法人を設立する旨」および「定款に記載すべき内容」を定めた場合にも、執行者の選任が必要です。設立手続きは非常に複雑であるため、実務経験のある司法書士などを選任することをおすすめします。(一般財団法人及び一般財団法人に関する法律第152条)
4.遺言執行者の主な役割
遺言執行者は、遺言の内容を実現するため幅広い手続きを担います。
相続が始まると、①まずは亡くなった方の戸籍謄本を取得して、相続人を調査し確定させます。②そして相続人に通知をし、③遺産を調査して相続財産目録を作成後、④遺言に従った財産の管理・引き渡しを行っていきます。その段階で、不動産の名義変更や銀行預金の解約・分配、遺贈などの手続きを全て行い、⑤完了後は相続人に報告をします。
さらに、相続人間の調整役としての側面も重要です。信頼と専門知識の両方が求められる役割といえます。
5.遺言執行者には誰がなれる?
遺言執行者には、未成年者や破産者を除き、誰でもなることができます。相続人や友人でもOKです。
しかし、相続手続きには多岐にわたる専門知識が必要となるため、一般の方がすべてをこなすのは容易ではありません。そのため、司法書士・弁護士などに依頼するケースが多く見られます。これらの専門家を遺言執行者に指定しておけば、安心して任せることができます。
6.遺言執行者を選ぶなら専門家へ
遺言の内容を確実に実現するために、遺言執行者は欠かせない存在です。あらかじめ遺言で指定しておけば、遺言者の意思どおりに手続きが進められ、家族は安心して相続を迎えることができます。
家族への思いやりとして、そして「自分の意思を確実に残す」ために、専門家を遺言執行者として指定しておくことを強くおすすめします。
遺言の作成を考えている方は、北千住のゆかり法務事務所へお気軽にご相談ください。足立区・葛飾区で相続・遺言に強い司法書士が丁寧に対応いたします。
遺言・相続はゆかり法務事務所へ
\ 電話・LINE・メール・微信で /
お問い合わせを受付中
東京都足立区千住中居町17-20 マルアイビル 6階 北千住駅から徒歩8分

行政書士
岡野 由佳梨

行政書士 岡野 由佳梨
専門家としての知識だけでなく、人として寄り添う姿勢を大切にし、ご本人にとって最善となるご提案を心がけています。どんな小さなことでも、お気軽にご相談ください。