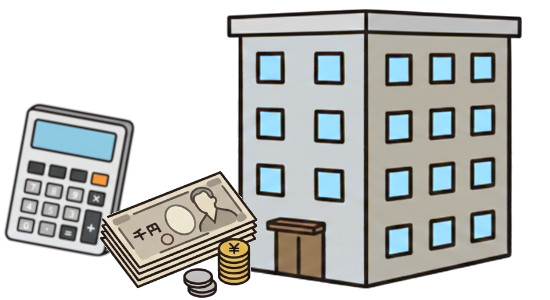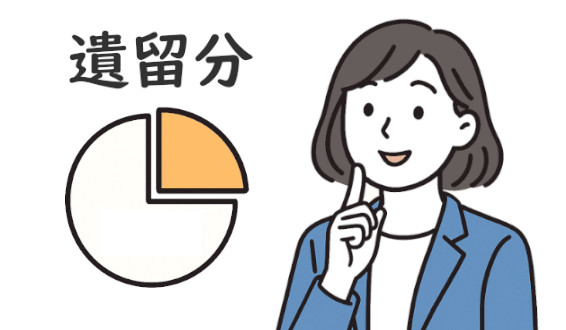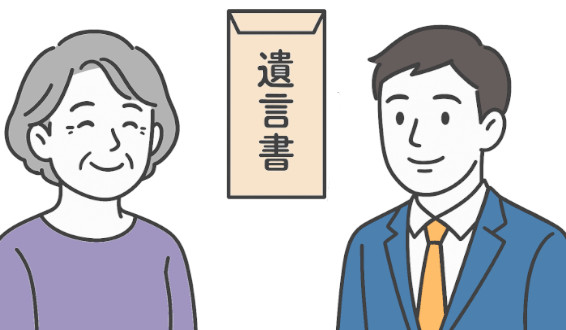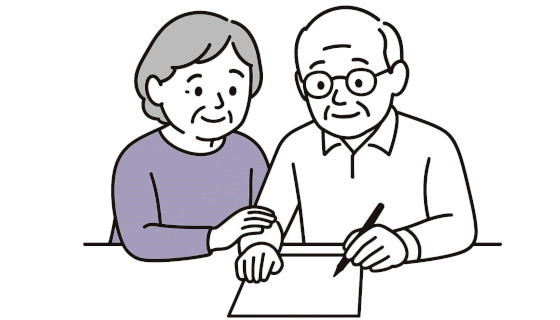遺言書を作りたいけれど「わざわざ公正証書にする必要があるの?」と思うかもしれません。確かに、自筆証書遺言に比べて手間も費用もかかります。
しかし、公正証書遺言には“無効になるリスクが極めて低い”“確実に実現される”という大きなメリットがあります。この記事では、公正証書遺言の作り方、費用の目安などを司法書士がわかりやすく解説します。
1.公正証書遺言を作成するメリット
公正証書遺言とは、法律の専門家である公証人が作成し、保管する遺言書のことです。遺言者と証人2名の立ち合いのもと、口頭で内容を確認し、全員が署名することで作成します。手間や費用はかかりますが、その分大きなメリットがあります。
1-1.無効になる心配がほとんどない
自筆証書遺言では、署名や日付の記載、訂正方法などの形式を一つでも誤ると、遺言そのものが無効になるおそれがあります。せっかく作成しても、それによって効力を失う事例は少なくありません。
その点、公正証書遺言は、公証人という専門家が関与して作成するため、形式不備はありえません。さらに、本人の意思を直接確認するため、「本人の意思ではなかった」と争われるリスクも低くなります。遺言の中で、最も信頼性の高い方法といえるでしょう。
1-2.改ざん・紛失・隠ぺいのリスクがない
公正証書遺言は、原本が電子データで保管されるため、紛失や「勝手に処分される」「内容を書きかえられる」といった心配が全くありません。
本人には正本や謄本というコピーが渡されますが、万が一紛失しても、原本が保管されているため再発行することができます。また、公正証書遺言があるかどうかは、無料で調べることができます。
1-3.家庭裁判所での検認が不要
自筆証書遺言の場合、相続の開始後に検認を受ける必要があります。検認とは、家庭裁判所で、相続人の立ち会いのもと遺言書の内容を確認する手続きです。書類を揃え申立てをし、亡くなった方の住所地の裁判所に出頭するなどかなりの手間がかかります。
一方、公正証書遺言は検認が不要です。相続の開始後は、すぐに預貯金の名義変更などの手続きを始めることができます。
1-4.手書きする必要がない
自筆証書遺言では、その全文を自分の手で書く必要があります。字が読みにくかったり、記載を間違えたりすると訂正も大変で、特に高齢者の方には大きな負担となります。
一方、公正証書遺言では、手書きするのは、署名部分だけです。病気などにより署名ができないときは、それに代わる措置をとることもできます。
2.公正証書遺言の作成手順
step1.専門家へ依頼する
スムーズに作成するために、最初に司法書士や行政書士などに相談すると安心です。
公証人は、本人の意思に従い作成する立場のため、「誰に何を相続させるべきか」「遺留分に配慮すべきか」といった内容の相談には応じられません。専門家に相談することで、思いを実現するためのベストな方法を知ることができます。
▼
step2.遺言内容の相談・作成
「誰に、どの財産を、どのように相続させるか」を相談して決めていきます。財産の分け方にも様々な方法があり、遺留分も考慮しなければなりません。
また、本人の身分証明書・戸籍などのほか、不動産の登記簿や預金通帳など、財産の内容を証明する書類を揃え、専門家がご相談いただいた内容をもとに文書を作成します。
▼
step3.公証人との打ち合わせ
専門家が公証人と打ち合わせを行い、正式な文書を完成させます。遺言者の意思が明確に反映されているか、法令違反やあいまいな表現がないかをチェックし、必要に応じて修正します。
また、必要に応じて証人の手配をし、遺言書の作成日を決めます。
▼
step4.公証役場で遺言書を作成する
作成の当日には、本人と証人2名が公証役場へ出向きます。
公証役場では、公証人が遺言内容を読み上げ、本人がその内容を確認し、意思確認を行います。誤りや不明点があれば、その場で修正することも可能です。問題がなければ署名し、完成です。遺言書の正本と謄本(コピー)を渡されます。
3.公正証書遺言の作成にかかる費用
3-1.公証人に支払う費用
公証人への手数料は、「公証人手数料令」という法令で定められており、財産の金額に応じて変動します。また、遺言書の枚数が多い場合や、公証人が病院や自宅に出張する場合には、日当や交通費が加算されます。
| 目的の価額 | 手数料 |
|---|---|
| ~50万円 | 3000円 |
| ~100万円 | 5000円 |
| ~200万円 | 7000円 |
| ~500万円 | 1万3000円 |
| ~1000万円 | 2万円 |
| ~3000万円 | 2万6000円 |
| ~5000万円 | 3万3000円 |
| ~1億円 | 4万9000円+超過額5000万円までごとに1万5000円 |
| ~3億円 | 10万9000円+超過額5000万円までごとに1万3000円 |
| 10億円超~ | 29万1000円+超過額5000万円までごとに9000円 |
※ 全体の財産が1億円以下のときは、1万3000 円が加算されます。
※枚数が3枚を超える場合には、超えた分は1枚当たり300円が加算されます。
※ 遺言者には、公正証書の内容を記録・記載した電子データ・書面を交付するので、その手数料が必要になります。
電子データの場合は各1通当たり2500円、書面の場合は、書面の枚数に300円を乗じた額となります。
※ 公証人が病院等に赴いて作成する場合、50 %加算されるほか、公証人の日当(1日2万円。ただし4時間以内の場合1万円)と交通費がかかります。
公証人の費用の計算例:
1億円の財産を配偶者に6000万円、子に4000万円相続させる場合
=4万9000円(配偶者の証書作成費用)+3万3000円(子の証書作成費用)+1万3000円(遺言加算)
3-2.専門家への報酬
司法書士や行政書士などに公正証書遺言の作成を依頼する場合、文案作成・書類収集・公証人との調整などに対して報酬が発生します。報酬の相場は、遺言内容の複雑さによって異なりますが、一般的には 5万円~15万円程度が目安です。依頼することで、書類準備から公証役場とのやり取りまで任せられ、安心して手続きを進められるメリットがあります。
3-3.証人に支払う費用
作成には証人2名の立ち合いは必要となるため、その人達へ支払う報酬も必要です。金額は、頼む相手により変わります。
4.公正証書遺言を作成するなら専門家へ相談しよう
公正証書遺言は、他の方式と比べて費用や手間がかかるものの、その分だけ確実性と安心感が得られる遺言書です。無効になる心配が少なく、家族に負担をかけずに、自分の意思を確実に実現できます。
ただし、公証人は、遺言者の意思を正確に文章化する立場であり、遺言の内容そのものについての助言や提案は行えません。遺言内容の検討や文案作成の段階では、司法書士や行政書士などの専門家に相談し、ご自身の思いを最も適切な形で遺言に反映させましょう。
公正証書遺言の作成を考えている方、お悩みがある方は、ゆかり法務事務所にご相談ください。初回相談では、相続人や財産の状況、希望内容を丁寧にヒアリングし、必要な書類や進め方をご案内します。
遺言・相続はゆかり法務事務所へ
\ 電話・LINE・メール・微信で /
お問い合わせを受付中
東京都足立区千住中居町17-20 マルアイビル 6階 北千住駅から徒歩8分

行政書士
岡野 由佳梨

行政書士 岡野 由佳梨
専門家としての知識だけでなく、人として寄り添う姿勢を大切にし、ご本人にとって最善となるご提案を心がけています。どんな小さなことでも、お気軽にご相談ください。
あわせて読みたい
5.よくある質問
Q. 公正証書遺言とは?
A. 公正証書遺言とは、法律の専門家である公証人が作成し、公証役場で保管する遺言書のことです。遺言者と証人2名の立ち合いのもと、口頭で内容を確認し、全員が署名することで作成します。
紛失や偽造のリスクが無く、無効になる可能性も低いというメリットがあります。
Q. 公正証書遺言の作成には、どれくらいの費用がかかる?
A. 財産額に応じて異なりますが、一般的に2万円〜5万円程度が公証人手数料の目安です。これに加えて専門家への報酬として、5万円〜15万円程度がかかる場合もあります。
Q. 公正証書遺言を作る時に証人は必要ですか?
A. はい、公正証書遺言を作成する際は、証人2名の立ち会いが必要です。未成年者や、推定相続人・受遺者・これらの配偶者および直系血族などは証人になれません。
Q. 遺言者が亡くなったときに、公証役場から相続人に通知は来ますか?
A. いいえ、公証役場から相続人に対する通知はおこなわれません。公正証書遺言があるかどうか確かめるためには、①遺品の中に正本・謄本(コピー)があるか探す、②公証役場に遺言検索を依頼する、といった方法をとる必要があります。