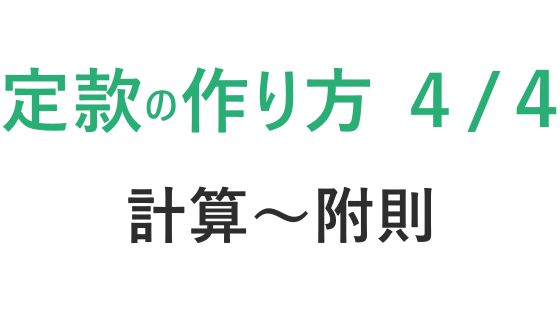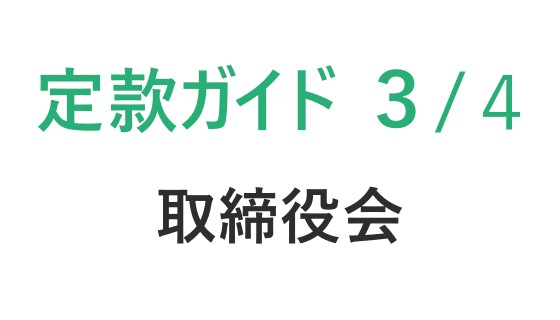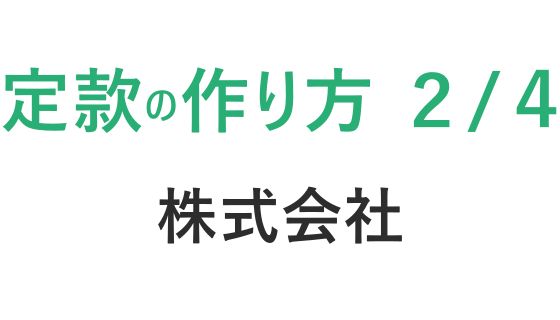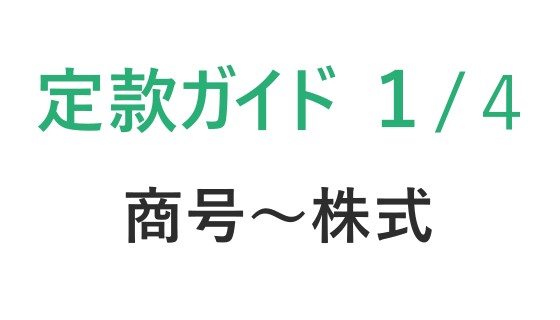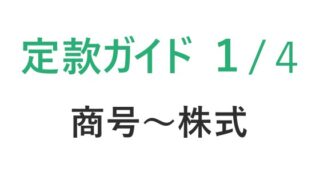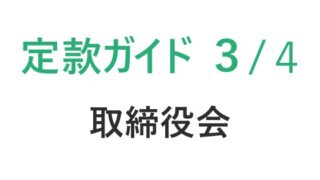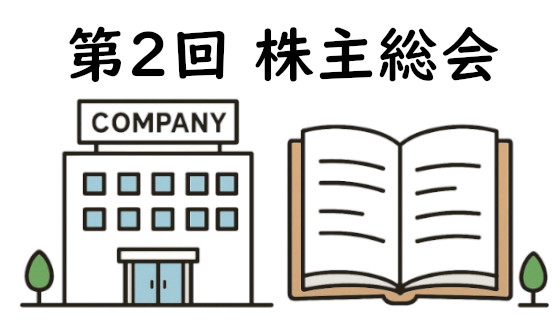
定款のひな形はインターネットで手に入りますが、意味を理解せずにコピペしてしまうと、後々トラブルの元になることも。
定款に盛り込むべき内容や注意点などを1条ずつ説明しますので、ぜひご活用ください。
この記事(第2回)で解説している条文
第12条:株主総会の招集
第13条:株主総会の招集手続の省略
第14条:議長
第15条:決議の方法
第16条:株主総会の決議の省略
第17条:議決権の代理行使
第18条:株主総会議事録
他の条文は第1回、第3回、第4回へ
1.定款とは?
定款とは、会社の基本ルールを定めた文書です。
定款には、会社の名前・事業目的・本店所在地・設立時の出資など、会社運営の根本に関わる条文が記載されます。本記事以外の条文も、下記ページで解説していますので、ぜひご覧ください。
●【第1回】定款の作り方(商号~株式まで)
●【第3回】定款の作り方(取締役~取締役会まで)
●【第4回】定款の作り方(計算と附則)
2.1条ずつ解説|記載例とその解説
2-1.第12条:株主総会の招集
第12条 当会社の定時株主総会は、毎事業年度末日の翌日から3か月以内に招集し、臨時株主総会は、必要に応じて招集する。
2 株主総会は、法令に別段の定めがある場合を除くほか、取締役の過半数の決定により社長がこれを招集する。
3 株主総会を招集するには、会日より1日前までに、株主に対して招集通知を発するものとする。
4 前項の通知は、書面ですることを要しない。
本条は、株主総会の開催時期と招集方法を定めるものです。
定時株主総会は、主に計算書類の承認・役員選任などの議題を扱うため、事業年度終了後に速やかに開催されるべきものです。
臨時株主総会については、「必要がある場合に招集できる」とすることで、役員変更や重要な会社方針変更時にも柔軟に対応できます。
株主にとって、株主総会の開催・招集は重要な事柄であるので、定款内でその招集の方法を明らかにしておくことが一般的です。
取締役会を設置していない会社は、小規模で利害関係者が少ないことが想定されるため、任意のタイミングで招集することができます。一方、取締役会を設置している会社は、ある程度の規模があり利害関係者も多いと想定されるため、必ず1週間以上前に開催通知を書面等で通知する必要があります。
2-2.第13条:株主総会の招集手続の省略
第13条 株主総会は、その総会において議決権を行使することができる株主全員の同意があるときは、招集手続を経ずに開催することができる。
原則として、株主総会の開催には事前の招集通知が必要ですが、全株主の同意がある場合に限り、招集手続きを省略することが可能になります。
たとえば、代表取締役が全株主でもあるケースでは、いちいち招集通知を送ることは実務的に意味が薄いため、この条項によって柔軟な運営が可能になります。ただし、「全員の同意」が必要であるため、1名でも反対した場合は通常の招集手続きが必要になる点には注意が必要です。
2-3.第14条:議長
第14条 株主総会の議長は、社長がこれに当たる。
2 社長に事故又は支障があるときは、当該株主総会で議長を選出する
株主総会の議長は、一般的には、会社の業務執行を担う代表取締役が議長に就くケースが多いです。
定款でも代表取締役を原則とし、万一不在の場合の代替者(他の取締役等)を定めるのが通例です。議長の指定がないと、総会当日に混乱が生じるリスクがあるため、特に株主が複数いる会社では事前に定款で規定しておくことが望まれます。
2-4.第15条:決議の方法
第15条 株主総会の決議は、法令又は本定款に別段の定めがある場合を除き、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数をもって行う。
2 会社法第309条第2項に定める株主総会の決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
1項は、株主総会の普通決議の方法、2項は特別決議の方法を定めています。
一般的に、出席した株主の議決権の過半数で決議が成立しますが、重要な案件は、定足数(=会議成立に必要な出席者の数)を加えることで、より慎重な意思決定を図ることが可能です。
2-5.第16条:株主総会の決議の省略
第16条 株主総会の決議の目的たる事項について、取締役又は株主から提案があった場合において、その事項につき議決権を行使することができるすべての株主が、書面又は電磁的記録によってその提案に同意したときは、その提案を可決する旨の株主総会の決議があったものとみなす。
いわゆる「みなし決議」に関する定款規定です。通常、株主総会は物理的な開催が必要ですが、株主全員の同意が得られれば、実際に総会を開かなくても「決議があった」とみなすことができます。これにより、迅速かつ効率的な意思決定が可能になります。
ただし、「株主全員の書面または電磁的同意」が必要条件であり、1人でも同意しない場合は、実際の総会開催が必要になる点には注意が必要です。
2-6.第17条:議決権の代理行使
第17条 株主が代理人をもって議決権を行使しようとするときは、その代理人は1名とし、当会社の議決権を有する株主であることを要する。ただし、この場合には、株主総会ごとに代理権を証する書面を提出しなければならない。
この条文は、株主が総会に出席できない場合に他の株主に議決権行使を委任できる仕組みを定めています。遠方に住んでいる株主や高齢の株主にとって、物理的に出席できないことは少なくありません。この制度があることで、すべての株主の意思を反映しやすくなります。
「代理人は株主に限る」と制限を設けることも可能で、これにより、社外の第三者や利害関係者による不当な干渉を避けて、会社の意思決定を健全に保つことができます。
2-7.第18条:株主総会議事録
第18条 株主総会の議事については、法務省令で定めるところにより、その経過の要領及び結果を記載又は記録した議事録を作成し、議長及び議事録の作成に係る職務を行った取締役がこれに署名又は記名押印もしくは電子署名を行う。
株主総会の議事録は作成が義務付けられており、株主総会の内容・経緯・決議事項を客観的に記録する重要な文書です。
特に、後日紛争が生じた場合には、議事録が唯一の証拠となるケースもあるため、その正確性と保存が極めて重要です。
議事録の保存期間は10年間とされており、保管場所や閲覧請求への対応も含め、社内の文書管理体制を整備しておくことが求められます。
3.定款作成は慎重に。分からないときは専門家に相談を
この記事では会社設立を考えている方や、定款を自分で作りたい方のために、定款の条文を1つひとつ丁寧に解説しました。
定款は会社のルールを定める最も重要な文書です。ひな形を流用するだけではなく、自社に合った内容かを確認しながら、自分で作成する力をつけることは将来の経営にも役立ちます。
とはいえ、誤った定款は設立後のトラブルつながる可能性や法的リスクもあるため、必要に応じて司法書士など専門家に相談しながら進めることをおすすめします。
会社設立はゆかり法務事務所へ
\ 電話・LINE・メール・微信で /
お問い合わせを受付中
東京都足立区千住中居町17-20 マルアイビル 6階 北千住駅から徒歩8分

司法書士
劉 洋

司法書士 劉 洋
会社設立は、事業の第一歩であると同時に、今後の信用や成長にも大きく関わる大切な手続きです。分からないことや不安を一つずつ解消しながら、安心してスタートできるよう丁寧にサポートします。