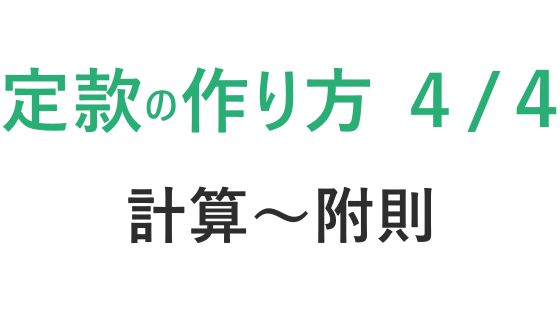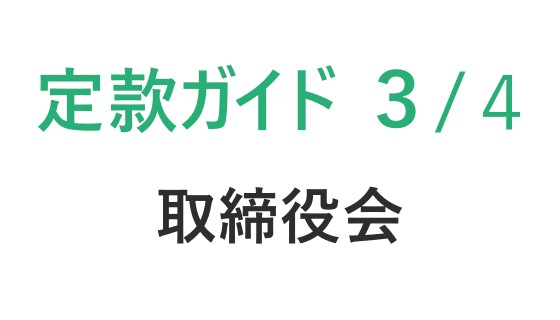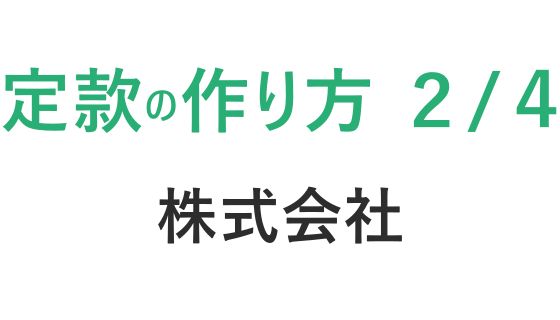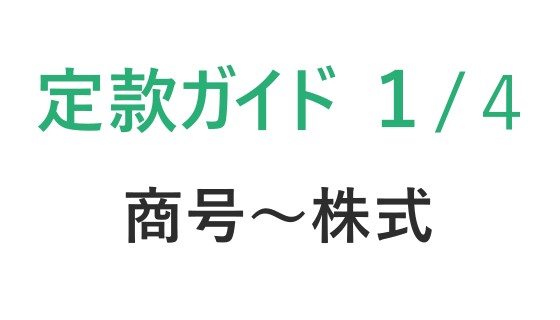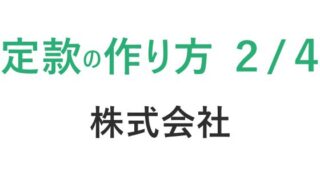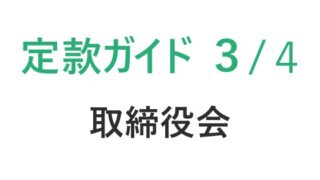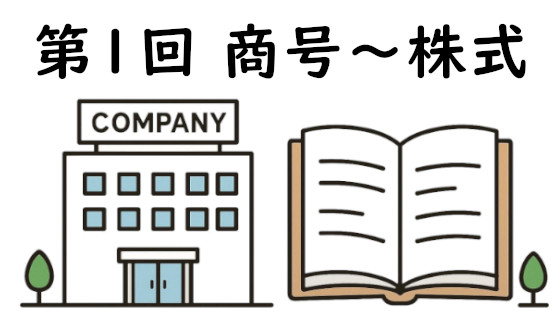
定款のひな形はインターネットで手に入りますが、意味を理解せずにコピペしてしまうと、後々トラブルの元になることも。
定款に盛り込むべき内容や注意点などを1条ずつ説明しますので、ぜひご活用ください。
この記事(第1回)で解説している条文
第1条:商号
第2条:目的
第3条:本店所在地
第4条:設立に際して出資される財産の価額
第5条:公告の方法
第6条:機関設計(取締役会、監査役など)
第7条:発行可能株式総数
第8条:株券の不発行
第9条:株式の譲渡制限
第10条:株式の基準日
第11条:株主名簿記載事項の記載の請求
他の条文は第2回、第3回、第4回へ
1.定款とは?会社設立に必要な理由
定款とは、会社の基本ルールを定めた文書です。
会社を設立するには、まずこの定款を作成し、株式会社の場合は公証人の認証を受ける必要があります。定款には、会社の名前・事業目的・本店所在地・設立時の出資など、会社運営の根本に関わる内容が記載されます。本記事以外の条文も、下記ページで解説していますので、ぜひご覧ください。
●【第2回】定款の作り方(株主総会まで)
●【第3回】定款の作り方(取締役~取締役会まで)
●【第4回】定款の作り方(計算と附則)
2.定款に絶対に書くべきもの
定款には、必ず記載しなければならない項目(絶対的記載事項)と、必要に応じて記載できる項目(任意的記載事項)があります。株式会社の場合、絶対的記載事項として最低限必要なのは次の5個です
① 商号(会社の名前)
② 目的(事業内容)
③ 本店所在地(市区町村まででOK)
④ 設立に際して出資される財産の価額、またはその最低額
⑤ 発起人の氏名と住所
これに加えて、取締役の人数や任期、公告方法(決算公告の掲載方法)などの任意的記載事を記載することが一般的です。これらの記載がもれると特定の効力が生じなかったり、運営に支障が出たりする可能性があります。
定款の構成としては、「第○条」といった条文番号で区切りながら記載していく形式が一般的です。次章では、実際の条文ごとにその意味を解説していきます。
3.1条ずつ解説|記載例とその解説
3-1.第1条:商号
第1条 当会社は、株式会社〇〇と称する。
定款の第1条は、多くの場合「商号」に関する条文です。商号とは、会社の名前のことを指します。
株式会社を設立する場合、「株式会社」という文字を必ず商号の前か後に入れる必要があります(会社法第6条)。
また、商号にはひらがな・カタカナ・漢字・アルファベット(ローマ字)・算用数字が使用できますが、同一住所での類似商号はトラブルの元になるため、事前に法務局やインターネットでの商号検索をしておくことが推奨されます。
⇒オンラインで商号調査する方法(法務省)
3-2.第2条:目的
第2条 当会社は、次の事業を営むことを目的とする。
1.不動産の売買、賃貸及び管理業務
2.インターネットを利用した物品販売業務
3.前各号に附帯関連する一切の業務
会社がどんな事業を行うのかを記載する「目的」は、定款の中でも特に慎重に書く必要があります。事業目的は、登記審査の対象となり、あまりにも抽象的すぎる表現や、公序良俗に反する内容は登記できません。
また、目的が曖昧だと、銀行口座の開設や融資、助成金の申請時に不利になる可能性があります。将来的に行う予定の事業も含めて幅広く記載しておくのが一般的です。
最後の「附帯関連する一切の業務」は定番ですが、無制限に使えるわけではない点にも注意が必要です。
3-3.第3条:本店所在地
第3条 当会社は、本店を東京都足立区に置く。
会社の主たる住所は、本店の「所在地」にあるとされています。
登記の際には、建物名まで含めた詳細な住所が必要になりますが、定款上は「東京都足立区」など最小行政区画までの記載があれば足ります。
3-4.第4条:設立に際して出資される財産の価額
第4条 当会社の設立に際して出資される財産の価額は金50万円とする。
設立時に出資される資本金の額は、会社の規模や信用に直結する重要項目です。1円でも設立は可能ですが、融資や取引の信用性を考慮し、数十万円~100万円程度を設定するのが一般的です。
3-5.第5条:公告の方法
第6条 当会社の公告は、官報に掲載して行う。
会社の決算公告や法定公告は、定款で方法を定める必要があります。
もっとも一般的なのは「官報」による公告です。新聞や電子公告も可能ですが、手続きの煩雑さやコスト面から官報公告が選ばれることが多いです。特別な事情がなければ「官報」で問題ありません。
3-6.第6条:機関設計(取締役会、監査役など)
第6条 当会社は、株主総会及び取締役のほか、取締役会及び監査役を設置する。
株式会社では、最低限「株主総会」と「取締役1名」が必須ですが、会社の規模や運営方針に応じて、取締役会、監査役、会計監査人、会計参与などの機関を設けるかどうかを選択できます。
小規模な会社では、取締役1名のみの「取締役会非設置会社」とし、意思決定のスピードを優先する形が一般的です。
監査役や会計監査人は、株主が多い、または事業規模が大きくなる場合に導入が検討されます。初めての起業では、運営コストや手間を抑えるために、最小限の構成とするのが現実的です。
3-7.第7条:発行可能株式総数
第7条 当会社の発行可能株式総数は、1万株とする。
発行可能株式総数とは、将来的に会社が発行できる株式の上限数を示すものです。
設立時に発行する株式数よりも多めに設定しておくことで、増資や第三者割当など資金調達を柔軟に行うことができます。
3-8.第8条:株券の不発行
第8条 当会社の株式については、株券を発行しない。
取り扱いが不便なため、現在では株券を発行しない会社が大半です。その旨を定款で明記しておくことで、株券発行の義務を回避できます。
3-9.第9条:株式の譲渡制限
第9条 当会社の株式を譲渡により取得するには、株主総会の承認を要する。
設立の際には、株式の譲渡制限を定めた非公開会社とすることが一般的です。これは、第三者への勝手な株式譲渡を防ぎ、経営の安定を図るための重要な条項です。
この条項がないと、相続や売買などで予期せぬ第三者が株主になる可能性があり、会社運営に支障が出ることもあります。経営者間の信頼関係を守るためにも、必ず入れておきましょう。
3-10.第10条:株式の基準日
第10条 当会社は、毎事業年度末日の最終の株主名簿に記載又は記録された議決権
を有する株主をもって、その事業年度に関する定時株主総会において権利を
行使することができる株主とする。
2 前項のほか、株主又は登録株式質権者として権利を行使することができる
者を確定するため必要があるときは、取締役の過半数の決定により、臨時に
基準日を定めることができる。ただし、この場合には、その日を2週間前ま
でに公告するものとする。
「基準日」とは、配当金の受け取りや株主総会への参加資格など、株主としての権利を確定するための判定日をいいます。
基準日を定款で定めておくと、都度公告する手間が省け、会社運営がスムーズになります。
3-11.第11条:株主名簿記載事項の記載の請求
第11条 株式取得者が株主名簿記載事項を株主名簿に記載又は記録することを請求するには、当会社所定の書式による請求書に、その取得した株式の株主として株主名簿に記載された者又はその相続人その他の一般承継人及び株式取得者が署名又は記名押印し、共同して請求しなければならない。
ただし、法令に別段の定めがある場合には、株式取得者が単独で請求することができる。
株主名簿は、会社が株主を把握・管理するための重要な帳簿であり、会社法上、会社は株主名簿を備え置く義務があります。また、株主となった者は、自身の情報を株主名簿に記載するよう会社に請求することができます。
この条項は会社法第130条に基づくもので、株主の権利を保護する役割を果たします。記載される事項には、氏名、住所、保有株式数、取得日などがあります。記載がなされていないと、株主としての権利行使(議決権、配当請求など)が制限される場合もあるため、非常に重要な項目です。
4.定款作成は慎重に。分からないときは専門家に相談を
この記事では会社設立を考えている方や、定款を自分で作りたい方のために、定款の条文を1つひとつ丁寧に解説しました。
定款は会社のルールを定める最も重要な文書です。ひな形を流用するだけではなく、自社に合った内容かを確認しながら、自分で作成する力をつけることは将来の経営にも役立ちます。
とはいえ、誤った定款は設立後のトラブルつながる可能性や法的リスクもあるため、必要に応じて司法書士など専門家に相談しながら進めることをおすすめします。
会社設立はゆかり法務事務所へ
\ 電話・LINE・メール・微信で /
お問い合わせを受付中
東京都足立区千住中居町17-20 マルアイビル 6階 北千住駅から徒歩8分

司法書士
劉 洋

司法書士 劉 洋
会社設立は、事業の第一歩であると同時に、今後の信用や成長にも大きく関わる大切な手続きです。分からないことや不安を一つずつ解消しながら、安心してスタートできるよう丁寧にサポートします。